礫床網状河川における護岸被害危険度評価
著者
- 阪上 健/広島大学大学院前期課程 先進理工系科学研究科社会基盤環境工学プログラム
- 内田 龍彦/広島大学大学院教授 先進理工系科学研究科社会基盤環境工学プログラム
- 松尾 大地/広島大学大学院後期課程 先進理工系科学研究科社会基盤環境工学プログラム
- 吉武 央気/パシフィックコンサルタンツ株式会社 河川部
- 坂野 アイカ/パシフィックコンサルタンツ株式会社 河川部
- 溝口 敦子/名城大学教授 理工学部社会基盤デザイン工学科
- 酒井 大介/国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所
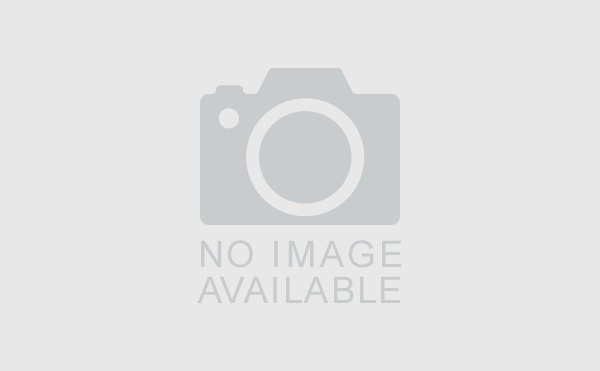
法政大学の原田と申します。発表をオンラインで拝聴しておりましたが、以下ご質問させていただきます。
・流れが護岸に与える力という点では、底面せん断力の方がより直接的な指標のように思えますが、「乱れ強度」が底面せん断力よりも護岸被災を判定するのに優れた指標だとお考えの理由について教えていただけますでしょうか。
・上記の点は、底面せん断力(あるいは底面流速)の左岸・右岸沿いの縦断分布と乱れ強度を比較すればより明確と思いますが、そういった比較は(既往研究を含め)されているのでしょうか。
・乱れ強度の式が流速(x,y方向)の絶対値ではなく「i方向(流れ方向?)」のみを参照するのはなぜでしょうか(理解が間違っていれば申し訳ありません)。
・流れが護岸に与える力という点では,底面せんだん力の方がより直接的な指標のように思えますが,「乱れ強度」が底面剪断力よりも護岸被災を判定するのに優れた指標だとお考えの理由について教えていただけますでしょうか.
対応:ご質問ありがとうございます.本研究で用いた乱れ強度は渦度の供給により流速鉛直分布が変形することで値が大きくなるため,底面流速が大きくなる個所だけでなく,二次流が発生する箇所,水面変動が大きくなる個所などを乱れエネルギーの増加で表現でき,流れの観点から,護岸被害の危険箇所を網羅的に検出することが可能と考えております.また,ご指摘の底面せん断応力はよく底面近傍流速から壁法則を用いて算出することが多いですが,乱れエネルギーも底面せん断応力で表現できます.実際,乱れが多いところでは乱れ強度を用いた方が河床変動を表現できることが分かっています(Simanjuntak et al, 2025).
Yogi Sahat Maruli Simanjuntak, Tatsuhiko Uchida, Takuya Inoue: Quasi three-dimensional calculation modeling for simulating partly 1 emergent rigid vegetation under fixed and movable bed conditions, Physics of Fluids 37 (6), 2025.
DOI: 10.1063/5.0263701
・上記の点は,底面剪断力(あるいは底面流速)の左岸・右岸沿いの縦断分布と乱れ強度を比較すればより明確と思いますが,そういった比較は(既往研究を含め)されているのでしょうか.
対応:ご質問ありがとうございます.種々の洪水,河川において,解析区間における河岸被災危険度評価において,局所的な流速(二次元解析の壁法則に対応)よりも,河岸際に発生する乱れエネルギーの方が高い精度で被災発生個所を検出できることが,以下の既往の検討で示されています.なお,著者らの調べでは,底面流速(準二次元解析の壁法則に対応)と比較しても,乱れエネルギーの方がより適切に護岸被害を抽出できました.これは洗掘や水面変動は水深平均流速や底面流速が小さい場所でも生じる可能性がありますが乱れエネルギーではこのような個所でも大きくなるためと考えられます.ただしこれらは固定床の検討であったためさらなる検討が必要と思っております.
高松潔明,永井秀和,内田龍彦,戸田祐嗣,重枝未玲,椿涼太,山下篤志,福田智子:乱れエネルギーを用いた河岸侵食危険確率の解析法とこれを用いた河川改修による流況改善の定量評価,河川技術論文集,Vol.27,pp.253-258,2021.
https://doi.org/10.11532/river.27.0_253
・乱れ強度の式が流速(x,y方向)の絶対値ではなく「i方向(流れ方向?)」のみを参照するのはなぜでしょうか(理解が間違っていれば申し訳ありません).
対応:スライド内の説明が不十分で申し訳ありません.乱れ強度の式におけるiは各方向(例えばx,y方向)を表し,アインシュタインの総和規約に則っています.
x,y方向で式を展開すると以下のようになります.
k=((4*Ch*Cμ)/(5*(Cε')^2))*(8*(∆ui)^2-7*(∆ui*δui)+2*δ(ui)^2)
=((4*Ch*Cμ)/(5*(Cε')^2))*{8*((∆ux)^2+(∆uy)^2)-7*(∆ux*δux+∆uy*δuy)+2*((δux)^2+(δuy)^2)}
松尾様
ご回答いただきありがとうございます、大変勉強になりました。
感覚的には、乱れ強度はそのセル単独の情報ではなく、隣接するセルの情報を含む指標ということで護岸の評価に用いられているのだと理解しました。その場合、格子サイズ次第で算出される乱れ強度はかなり異なるのではないか、また護岸付近が水際で水深が非常に浅くても適切に評価できるのか、護岸以外にも、乱れ強度を用いることができるのか、そういったことを考えました。
今後とも、いろいろと教えてください。ありがとうございます。
失礼しました、∆ux、δux等はz方向の差分で、平面方向には同じセルの情報ですね。
的確なご意見ありがとうございます.まず,格子サイズ依存の話ですが,数値解析のverification的には格子収束性を満たす必要がありますが,本研究では確認しておらず,ご指摘の通り,格子サイズにより乱れ強度は変化すると考えられます.また,水際についてですが,水深が非常に小さい場合にはその地点で方程式上は等流流速分布になり,乱れ強度は通常のゼロ方程式と同じになるため,乱れ強度は低くなります.しかし数値解析上は,適切に評価することができておらずしばしば振動などをする場合があり,ある程度以上の水深がある地点を抽出する必要があります.この点については算出法を決定することはできておらず,今後の課題と考えています.本論文では低水路と高水敷で計算格子を分けて作成しており,低水路際の計算点から乱れ強度を算出しています.最後に,護岸以外への適用性についてですが,乱れ強度は流れの三次元性の指標であり,堰直下流などの三次元性が高い箇所で高くなります.乱れ強度の平面分布を見ることで,護岸際だけでなく,河道内の流れの危険箇所についても検出することが可能であると考えています.